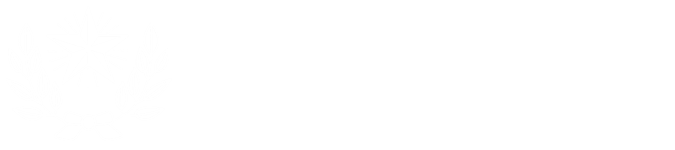八剱八幡神社 奉納「謡仕舞」(3/4)
今回は秀雲會の解説を取り仕切ってくれたOG(ヨハネ生)の声の前半をお届けします。

第一回 八劔八幡神社奉納 秀雲會 謡仕舞を終えて(前半)
ヨハネ研究の森を卒業して以来、私は一貫して大学で歴史学を学んでいる。歴史学とは、その名の通り私たちが連綿と受け継いできた「歴史」という営みを扱う学問である。
歴史とは、それ自体が紀元前以来の歴史を持っている。そのため、学問の俎上に上げる際には範囲や地域等を限定しなくてはならず、またある科学的な手法に基づいて扱う必要があるが、手法に関していえば、現在の日本の歴史学界においては、遺された史料からある出来事に関する歴史解釈や事実関係を実証する「実証史学」という手法が主流となっている。
その歴史は、戦後日本の歴史学界を席巻したものの、理論偏重のあまり実証性に乏しいことが問題視された「マルクス史学」に対する一人の若手歴史家の挑戦に端を発しており、歴史家の価値判断や思想をできるだけ排除し、「史料に語らしめる」という手法はおよそ半世紀に亘って、日本の歴史学界の標準となってきた。
このような歴史学界の潮流に則り、普段の私は基本的に、自身の研究テーマにまつわる史料を渉猟しつつ、それらが語りかける言葉に耳を傾けている。歴史家は、世間からは塵芥にしか見えないものを後生大事にする生きものであるが、私の場合も一見無機質で時に判読が困難な史料と対話しつつ、専攻する日本近代史の重大な一テーマである「軍部」の実際について、検討を進めながら過ごしている。
このように、普段「歴史」を相手にしているというと、多くの人は「随分と古いことに精通しているものだ」と買い被り、骨董品を見るような温かい眼差しを向けてくれるものである。「歴史」自体は連綿と続く流れであり、時代区分は便宜上設けられた区切りに過ぎないのであるが、私の専攻自体は最も新しい時代区分である「近代」であるため、そのような時には、たかだか2、3世代程度の時間軸ですよ、と恐縮しきってしまう。
とはいえ、確かにそれでもそれが「歴史」であることには変わりない。
しかし、やはりたかが1、2世紀の範囲を行き来し、およそ半世紀前に編み出された手法に基づいて研究を行っている身としては、650年の伝統や歴史と対面した「第一回 八劔八幡神社奉納 秀雲會 謡仕舞」への参加は、極めて稀有で貴重な、感動的な体験だった。
日本は、島国である。それは紀元前の大昔に大陸からはぐれて以来現在に至るまで変わらない環境であり、日本列島では「島」というアイデンティティーに多分に影響を受けつつ独特の伝統文化が様々に構築され、そのいくつかは現在に至るまで受け継がれてきた。
能楽師・秀雲先生を師とする「秀雲會」が今回、木更津の八劔八幡神社で奉納させていただいた「お能」も、連綿と受け継がれてきた日本独特の文化的営み、伝統芸能の一つである。その歴史は室町時代に遡り、爾来およそ650年に亘って、継承の担い手だけを幾度も変えつつ、厳密な形で受け継がれてきた。
それは、恰も甕から甕へ水を移すかのような営みであると思う。
ここでいう「甕」とは継承の担い手、即ち能楽師たちであり、「水」とは演目だけではなくお作法や振る舞い等も含んだ、お能そのものである。寿命により甕という器は変わっても、水という器は同じものを絶やさず受け継ぎ、それが21世紀の現代では「世界無形文化遺産」として、もはや世界的な演劇となっている。
時間が不可逆的なものである以上、650年の重みはそれだけで尋常ではなく、もはやその事実だけで既に一つの芸術であるような感がある。
そして、無数の甕が秩序立って並ぶ、その一番先に現代の能楽師である秀雲先生の姿があり、その傍らにはそこに与る私たちJohanna、ヨハネ生がいる。その光景は考えるほど不思議で幻想的ですらあるが、およそ1年前にはお能の「の」の字もなかった私たちが、歴とした神社のお舞台に立って奉納の謡仕舞をする、という夢のような出来事を私は「解説」というお役をいただいたことで目撃、現実に体験してしまったのだった。
(続く)