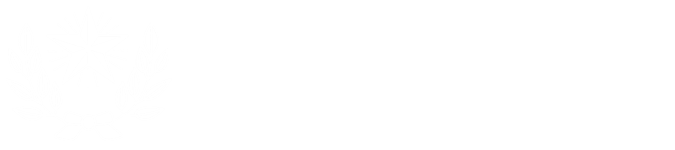2024年度サマースクールのご報告(3/4) 試験林にて
和穎先生と共に不耕起栽培と慣行栽培の土の違いを比較した後、私達は森に連れて行っていただきました。アスファルトの向こう、生い茂った雑草たちを乗り越え、木陰に入ると、その先は森の中です。枝葉に覆われてひんやりと涼しく、足元にはたくさんの落ち葉が積もり、歩くとさくさく音がします。先生を追いかけていくと、ピンクのピンが刺さっている場所にたどり着きます。ここでは特別に、土壌の層を見ることのできる土壌断面を見せていただきました。
先生がスコップを立てると、土の下からベニヤ板が現れます。穴を掘って板を渡したのは1年前とのことで、森の中ではたった1年でベニヤ板が隠れるくらいの土ができていることがわかります。土を払い、板を開けていただくと、深さ1mほどの大きな穴が現れました。中を見てみると、上の方の土は腐植で黒く、下に行くにつれ、少し明るい茶色になっており、土壌の層が形成されていることが分かります。特別に穴の中に入れていただきました。穴の中から大きな蜘蛛やミミズがぴょこぴょこと飛び出し、元気いっぱいのサマースクール生たちがすかさず捕まえていました。
また、森の中では、生き物たちの力が働き、細かく分解され、徐々に土に変わっている最中の落ち葉を実際に見ることもできました。森でよく見かける灰色っぽい落ち葉は、森の土にしかいない白色腐朽菌と呼ばれるキノコに分解された証拠なのだそうです。
フィールドワークを通して、良い土の中には多様な生き物が生きていること、生き物たちの力が働いて土ができていることを実感することができました。
研究所の建物に戻ってからは、地元つくばの美味しいお弁当を頂きながらセッションが行われ、「土は生きている」という言葉の所以に迫るようなダイナミックなお話があり、「土」に対するイメージが組み変わっていきました。